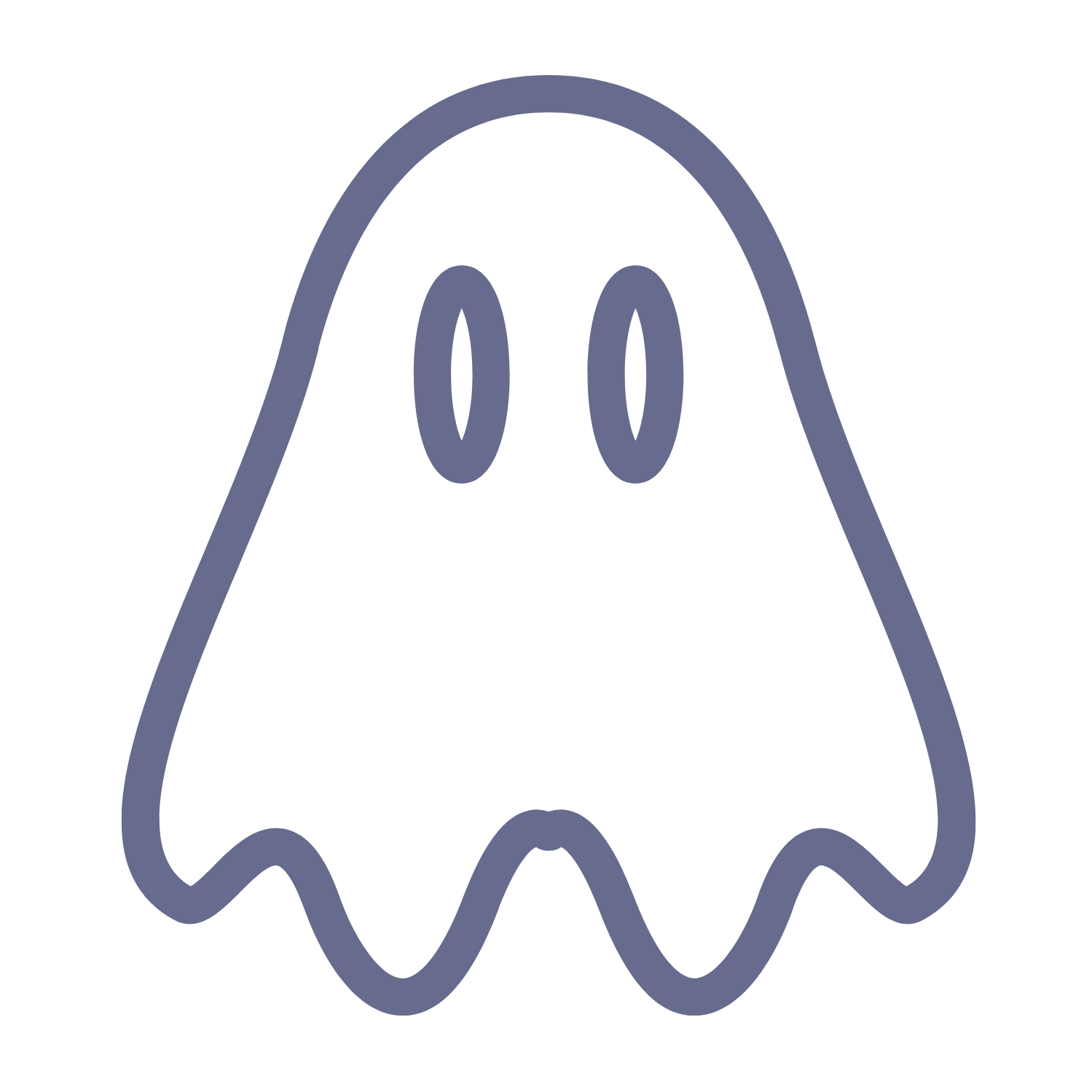Bullion『Affection』
このアルバムを聴いていると美術館の展示室をつなぐ通路のことが頭に浮かぶ。「順路」などと書かれた札が立ち、途中に休憩用のソファが置かれていたりする、あの廊下や階段のことが。そこは特に何もない、ただ通り過ぎるための空間にすぎない。そこは誰かが何かを感じるために用意された場所ではない。でも期せずしてと言うべきなのか、そこには新しい何かとの出会いに対する静かなときめきが漂っている。日常を離れた清潔で形而上的なマインドセットや、どのような展示にも対応する合目的的な端正さが備わっている。別の言い方をすれば、このアルバムの中には芸術作品が含まれていない。どこか常に虚ろで、つるりとした表面を持つこのアルバムは、あと一歩のところで本物の芸術作品になることに失敗している、あるいはそうなることを拒んでいるようなところがあって、その欠如のあり方が私を––––芸術的に––––惹きつける。
歌詞には「父性への憧れ」という主題が何度か出てくるが、中でも収録曲「World_train」の「僕にはどうしてもわからない/本当の男になるには何が必要なのか」という告白はその直接性ゆえに際立っている。自分が作っているのがいい作品なのかどうか疑ってしまうことが曲作りにおける最大のハードルであり、これまで2年以内に作り終えられた曲が1つもないと語っている彼の音楽からは、彫琢を重ねすぎることから来る隙のなさ、迷いの中で生きている人特有の自己防衛のようなものが感じられる。どう見てもポップ志向を持つ曲を作りながら、彼はまるで聴き手とのあいだに情緒的な関係を結ぶことをためらっているかのようだ。このアルバムの蕾のような固さは、しかしその内側で成熟の甘い夢に微睡みながらなまめかしく形を変えていく花弁の柔らかさを報せてもいる。無表情の背後に隠れることでしか伝えることのできない心の風景がここにはある。
MJ Lenderman『Manning Fireworks』
フォークロック~カントリーロックというジャンルが時代の空気を伝えるための手段として今なお有効どころか最適ですらあることを知らしめた、2024年最もウェルメイドな音楽。英語圏ではユーモアとひねりの利いたワードセンスが高く評価され、「ネクスト・ニール・ヤング」などとちょっとしたカルト的崇拝の対象に祀り上げられている。このアルバムが主として取り上げているのは、リベラルな知識層のおかげで権利意識が著しく向上した「正しい」アメリカ社会から思想的にも経済的にも取り残され、自堕落な生活を送っているクソ野郎(jerk)たちだ。彼らは仲間と酒を飲んだり女性にちょっかいをかけたりするが、自分と直接関係ないことには耳を塞ぎ、他人と心から触れ合うことはない。大切な人は離れていき、自分だけが孤独であるような感覚に苛まれ、心のどこかで助けを求めているが、やはり男性文化(ブロカルチャー)の心地良い殻の中からは出られずにいる。
驚くべきは、この25歳のアーティストが彼の出身地であり活動拠点でもあるアメリカ南部において今やむしろ支配的になっているこの荒涼とした情景をごくゆったりと受け止めていることだ。確かに彼の歌い方はちょっと疲れている。しかしその疲れをもたらしているものはみな柔らかに音楽化され言語化され、どの曲もぎりぎりのところでずっと「ゴキゲン」なままだ。「何も気にしていない人のように歌い、とても深いところで密かに気にしている人のように作曲している」というNYタイムズの鋭い指摘の通り、彼は歌の主人公たちへのたっぷりの諷刺とたっぷりの共感を込めた曲を演奏するにあたり、クールな距離を取って小説家さながらのクリアな筆致で市井の物語を伝えている。こうした極めて体幹の安定した音楽を可能にしたのがアメリカ南部本来ののんびりと構えた朗らかな風土なのだとしたら、なんと皮肉なことだろう。そしてこのアルバムは彼の故郷とそこに住む人々に対するなんと深い愛の行為なのだろう。
Mk.gee『Two Star & The Dream Police』
80年代というのは産業の勢いが強く、個々の人間の心の動きが比較的見えづらい時代だったような印象がある。音楽もその例に漏れずというか、多くの人が取り憑かれたようにドラムにゲート・リヴァーブをかけて音響的に画一性の高い作品を作ることになった。この人は今、その音楽を自分の心の最も秘めやかな部分を表現するために転用している。そこに彼の主客を転倒させるラディカルさがある。フュージョン、AOR、クラシックロックなど現在はあまりイケてるとは思われていない領域の鉱脈を一人でせっせと掘り進め、フェティッシュとすら言えそうなほどの限られた音のパレットを使って狭い音響レンジの中に細かいニュアンスをぎっしり詰め込んだ結果、一見輝きに乏しいオパールがその内側で複雑な色味を呈しているように、ローファイであると同時にハイファイであるような不思議な感触が生まれている。
自信のなさや犯した過ちに対する後悔、自分がなぜこうなのかわからない戸惑いを無防備に晒した歌詞にもかかわらず、私にとってこれは概して共感とかそういう類の感情を誘う作品ではない。どちらかと言えば高度な幾何学あるいはアクロバットとして美的・身体的に痺れる作品で、特定の刺激に対して他人の50倍細かい感覚を持っていたり、自分以外の誰も理解できない計算式があったりする人の遠さを感じる。言ってみればこれは孤独と孤高について、人はどれだけ個性的になり得るかについての音楽であり、誰も知らない世界に住む誰も知らない人間の実感が克明に記された報告書である。「こんなところまで来ましたよ」と彼が伝えるその場所に私たちはこれまでもこれからもおそらく決して行くことはない。でもそこは宇宙や深海と同じように、私たちがこのように生きることになったそもそもの経緯、私たちの意識の成り立ちについて、存在そのものによって語っている。
すずめのティアーズ『Sparrow’s Arrows Fly so High』
日本の民謡を現在の西洋化した音楽の観点から解釈した作品はこれまでもあったが、このアルバムが特殊なのは、2人の歌い手による「ハモり」が演奏の中心に置かれていることだ。合いの手はあっても和音(コード)や和声(ハーモニー)の概念がなかった日本民謡にとって、ここでは本来あり得ない、「今」としか言えないことが起こっている。一方で、アルバム全体にわたって重なり続ける2つの声は、かつてそれぞれの曲を実生活の中で歌っていた人々の心の陰翳を強調するように民謡に宿る魂を立体的に投影し、いわば4Kレストア的に「オリジナルよりもオリジナル」な形で現代に甦らせてもいる。その眩暈のするような濃い霊体はまるでブラックホールのようにその引力によって時空を歪め、民謡を現代化・西洋化するというより、ジャズの構えを持つバックバンドの演奏を「過去化・日本化」している。だからこのアルバムを聴いていると「日本にはこんな良い音楽があったのか」と各曲の正調(伝統的な奏法)ヴァージョンも聴きたくなってくる。
収録曲の多くは労働の最中に歌われた作業歌や一種の営業活動のために人家の軒先で歌われた門付歌だが、歌詞には性や恋や別れなど、階級社会において主に女性たちが限定された主体性の範囲で切り抜けるほかなかったライフイベントにまつわる話題が地続きで現れる。離ればなれになったものを1つにしたい、1つだと思われているものの中にある引き裂かれた思いを白日の下に晒したいという歌詞の中にわずかに感じ取れる彼女らの願いが、ハーモニーの使い方ひとつで、バンドの精妙な演奏にも助けられて、美しく、逞しく、妖しく、可聴域まで増幅されている。私たちの体内のどこかに今もあるはずなのに近代化の流れの中でアクセスできなくなってしまった日本的情念に時間の跳び越えによって到達したと思ったら普遍的な人間性にまでたどり着いてしまい、ブルガリアやトゥヴァ共和国の音楽へと空間をも跳び越えていくことにもギミックではない自然な説得力がある。
Cindy Lee『Diamond Jubilee』
似たような顔をした小柄な佳曲が並び、弱めのボディーブローが続く、最近ではめずらしい極端にアルバム志向のアルバム。タイトルは「60周年祝典」の意味(日本でも結婚60周年のことを「ダイアモンド婚式」と言うように)で、この作品が直接的な影響を受けているガールグループ音楽が1960年代初頭に花開いたことなどによる、ジャンルとしてのポップ・ミュージックの誕生からの時間のことを指しているのではないかと個人的には推測している。またそれはおそらく永遠の愛のことも示唆しており、大好きだった人の死を受け入れられない苦しさがアルバム全体を貫く経糸になっている。膨大な時間のかかるその「長いお別れ」の過程を描き出すために全32曲、122分という映画のような長さを要しており、甘い夢と記憶に浸り続ける序盤、石のように冷たい現実と向き合わざるを得なくなる中盤を経て、希死念慮すら口にする22曲目「Deepest Blue」で底の底まで落ちてから歌い手は徐々に前を向き始める。
どんなときも寄り添ってくれる黎明期のポップソングの懐の深さを頼りに、このアルバムは人間が一生の中で抱く最も強い感情の数々(および感情の喪失)を表現している。だがそれだけではない。それはあらゆる幸不幸のさらに一段奥にあってすべての原因となっている「時の流れ」をも視野に入れている。遠い昔に誰かがエアチェックしたラジオ音源と言われてもわからないような靄のかかった音楽は、ミュージシャンたちが年を取り、やがていなくなった後も残り続ける思念、過去の音楽の亡霊たちと、生死の境界をまたいで交信しているかのようだ。私の考えでは、これは「死すべき人間(mortals)が時間を乗り越えて永遠(immortality)に到達する手段としての音楽」についてのコンセプト・アルバムであり、「新しさ」や「自分らしさ」という個別の音楽作品が一般に持つべきとされている価値はあらかた放棄されている。芸術は長く、人生は短い。すべてが過ぎ去ってしまうことから来る人生の基本的なきつさは、芸術の中でその意味を反転させ、誰にも占有されることのない宝石へと結晶して万人に輝かしく開かれている。