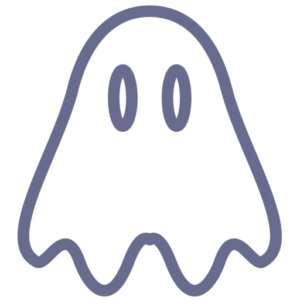映画館で映画を観ているとき、たまに自分にとって本当に大切な何かを思い出すような感覚を持つことがある。普段は忘れているが、それさえ憶えておけばこれからはもっとしっかりと、もっと自分らしくこの一度限りの人生を歩んでいけそうな何かを。それは鮮烈であると同時にとても微妙な感覚なので、私の場合せいぜい一晩も経てば砂の城が波に攫われるように日常の力に押し流されて跡形もなく消えてしまう。それでも何かしら大事なことがあったなという記憶だけは残って、「あの映画は好きだ」という、日常の持ち運びに適した頑丈でありふれた感想に置き換えられる。
ポーター・ロビンソンの7年ぶりの2ndアルバム『Nurture』(2021、MOM + POP)を初めて聴いたときに感じたのはそのような感覚、とりわけ日本のアニメ映画が表現することを得意としている種類の感覚に近かった。ふとしたきっかけで突然断絶してしまう日常生活。生と地続きで存在する死の生々しい感触。試練を経た主人公が自らの運命を再発見するときに訪れる超越的な瞬間。どこかJ-POPにも似た雰囲気を持つ『Nurture』の収録曲は、それぞれがその種の日本的なテーマ––––強引に一言でまとめてしまうなら、時間の不可逆性から来る切なさのようなもの––––を扱っているように感じられた。そして音楽の良いところは、ものの数分もあればあの精妙な砂の城を簡単に「再生」することができるということだ。
コロナ禍のためにリリースを1年遅らせた影響で曲数が増え、最終的に全14曲、1時間に届かんとするアルバムとなった『Nurture』で私が最も強く心動かされたのは、2ndシングルでもある11曲目の「Something Comforting」だった。
優しい心がその優しさゆえに抱え込むことになってしまった屈託を表したようなアルペジオで始まるこの曲の中では、全部で3回繰り返されるサビが少しめずらしい変化の仕方をする。1回目(0:39~)は、女性ヴォーカルが単独で歌う。2回目(2:26~)は、女性ヴォーカルの声が途中でポーター・ロビンソンの声に切り替わり、そこから彼と女性がユニゾンで歌う。3回目(3:36~)は、2人のあいだの声の切り替わりが初めから終わりまで頻繁に繰り返される。そこで彼らはこのように歌っている。
‘Cause getting made you want more
And hoping made you hurt more
Oh, there must be something wrong with me
And getting made you want more
And hoping made you hurt more
Someone tell me something comforting
手に入れるほど欲しくなって
希望を持つほど傷つくなんて
ああ自分はきっとどこかがおかしいんだ
手に入れるほど欲しくなって
希望を持つほど傷つくなんて
誰かかけてくれないか 励ましの一言を
曲が進むにつれ、女性とポーター・ロビンソンが抱く思いは互いに接近していき、最後には同じ1つの気持ちを共有する。誰かが歌っている歌はその人個人だけのものではなく、どこか別の場所でそれを聴いている別の誰かのためのものでもある。この曲のヴォーカルの切り替えは、このサイトでもたびたび言及してきたポピュラー・ソングのそんな美しい機能を実演してみせているように思えた。
……もちろん曲をどのように受け取るかは聴く人それぞれの自由だ。今も私は基本的にはそのような聴き方でこの曲を聴いているような気がする。しかし、ポーター・ロビンソン自身の実情について言うなら、彼がこの曲に込めた意味はそれとはまったくかけ離れたものだった。
アメリカにおけるEDMシーンの本格的な夜明け間際、ダフト・パンクの『Discovery』を主たる起源として興ったエレクトロハウスに「コンプレクストロ(complex複雑な+electroエレクトロ)」と自ら名づける緻密で繊細なヴィジョンを持ち込むことによって、まだ高校生のうちに名を馳せたポーター・ロビンソン。彼は性格的にも繊細な部分を持ち合わせていた。ネット上で発表した音源が音楽販売サイトBeatportのチャートで1位を獲得するなど話題を呼び、2011年、スクリレックスが新たに発足させたレーベル<OWSLA>の第1弾リリースとしてEP『Spitfire』を19歳でリリースした頃から、彼は学校でもさほど目立つ生徒というわけではなかった自分がEDM界の寵児としてファンや批評家からの注目の的になっていることに、強烈な––––やや強烈にすぎる––––喜びを感じるようになる。
初めて国際的にツアーをするようになったのは18か19の頃だった。僕は高校ではただのオタク系の人間で、純粋に楽しいから、成功しようなんてまったく考えもせずにコンピューターでビートを作っていた。でも毎週金曜日の午後になると、僕は学校を出て飛行機に飛び乗り、夜にはショーをやっていた。土曜の夜にもショーをやって、日曜日にはまた飛行機で帰ってくるような生活だった。そして人々は僕が何をしているかについての文章を書いていて、僕は大人たちから誇らしく思われるという、成功の最初の薫りを味わっていた。それが僕のアイデンティティを深刻なかたちで形成しなかったと言えば嘘になる。僕は本当に中毒になっていて、そこから得られる自尊心の感覚に心底夢中になっていた。
Song Exploderのインタビューから(2021年4月21日掲載)
「中毒」になるほど世間の評判を気にしてしまう理由、それは彼が自分自身に対して極度に厳しすぎることだった。
僕は完璧主義者で、ときどき自分自身が自分の最大の敵になってしまって、ソーシャル・メディアから自尊心の感覚を得ていた。僕は自分に対して本当に厳しくなりやすくて、批評に本当に影響を受けてしまう。このことについて実はすごくよく考えるんだ。
The Forty-Fiveのインタビューから(2021年2月12日掲載)
現在の自分を否定しながら理想を追い求める性格は良い方向にも作用した。「2014年までの時点で、EDMはそれ自体の度を越した戯画みたいなものに変わり果てていた」と彼は上と同じThe Forty-Fiveのインタビューで語っている。「僕は自分の音楽も、あのころ周りの人たちがやっていた音楽も好きじゃなかった。EDMのパーティー・チューンなんてもうかけたくなかった––––もっと内省的になりたかった」。そんな中リリースされた、かねてから彼が心酔していたゲームやアニメや映画や本の世界への没入感をインディー・ポップの文脈から具現化したデビュー・アルバム『Worlds』(2014)は、商業的にも批評的にも大成功する。
だが彼の中の悪魔は––––彼がいつも恐れていたというツイッター上での批判と同じように––––彼に語りかけることをやめない。自分だけのサウンドを確立した手応えを得ることができた『Worlds』のツアー後、スタジオに戻った彼は次に自分が作るものに対して「クールな人々」がどのように反応するかを過度に気にした状態になり、プレッシャーと恐怖心に苛まれるようになる。満足のいく曲が作れずにいるのは努力が足りないからだと考えた彼は、音楽制作以外のことに時間を費やすことに罪悪感を覚え、友人と会うことも、恋愛をすることも、音楽を聴くことも、ゲームをすることも、映画を観ることも、新しい技術や楽器を試してみることもやめてしまう。ちょうどその頃、自身の未発表音源がリークし、ファンの一部がビットコインを使ってそれを売買していること、仲の良かった17歳の弟が稀なタイプの悪性リンパ腫に罹っていることが判明する(現在は無事快復)。
鬱や不安、強迫性障害の症状に悩まされるなか、彼は自分という人間の存在価値はすべて自分の作る音楽の成否に懸かっていると考え、「自分を証明するために」、「自分がまだ音楽を作れることを自分に対して示すために」(FADERのインタビューから)、スタジオに入るようになる。しかしそう強く思えば思うほど閃きは遠ざかっていき、彼は生まれて初めて音楽をまったく作ることができなくなる。Zach Sang Showのインタビュー動画によれば、早くから音楽の世界に入り、自分には他にできることが何もないと感じていた彼にとって、それは「生か死かの問題」にすらなっていたという。この時期(2016年8月)に彼のこれまでのキャリアで最もよく聴かれている曲「Shelter」(『あの花』を手掛けたA-1 Picturesによるアニメーションで話題になった)がリリースされていることには驚くほかないが、この曲は10代前半からオンライン音楽制作コミュニティでしのぎを削り合ったマデオンとの共作であり、ポーター・ロビンソンが提供したトラックやヴォーカル・チョップは『Worlds』制作時に作った曲を使用したものだった。「マデオンはアルバム3枚分くらいの曲を作ってくれたのに、僕が彼に見せられるものは何ひとつなかった」と彼は同じ動画で語っている。
2015年から2017年にかけて続いたこの混迷期の中でも最も深い落ち込みの渦中にあったある日、ニューヨークでタクシーに乗っていた彼にひとひらのメロディーが舞い降りてくる。それはのちに「Something Comforting」のドロップ部(1:06~)となるメロディーだった。そこに乗せる歌詞や、その前後に連なるメロディーはどうしても思いつかなかった。もう一度アルバムを出せるようになるまでの道のりは果てしなく遠かった。しかし少なくとも自分にはこれがあるのだと考えた彼は、そのメロディーを録音したものを「1万回かそれ以上」は聴き返したという。
2017年初めには日本生まれの恋人ができ、彼はまた––––実に2年以上ぶりに––––少しずつ生活を楽しむことができるようになっていく。プレッシャーから逃れるために別名義のヴァーチャル・セルフとして制作を進め、同年11月にリリースしたシングル「Ghost Voices」はグラミー賞にもノミネートされる。さらに彼には『Worlds』をリリースする少し前に観ていた、ある日本映画のことが頭にあった。その映画を観たとき、彼は「『Worlds』の後に自分の音楽が目指すのはこういう方向になるだろう」と確信していたのだ。実際、その映画は7年の時を超え、完成した『Nurture』に甚大な影響を与えることになる。
このアルバムに対する『おおかみこどもの雨と雪』の影響は火を見るより明らかだ……あの映画を観て僕に起こったのは、何を美しいと思えるかについての感覚ががらりと変わってしまったということだった。遠くにあるものとして見てきた「感情」や「美」や「音楽」をものすごく身近にあるものとして見るようになるというその転換を一度経験してしまうと、まるで目の前で世界が開けたようになった。僕にとってすごく啓示的だったのは、あの映画のサウンドトラックを聴いたことだった。それは高木正勝によるもので、映画を観て以来、彼は僕の四大音楽ヒーロー※の1人になった。
※彼の別の箇所での発言から察するに、残りの3組はダフト・パンク、カニエ・ウェスト、ボニーヴェアであるようだ。
FADERのインタビューから(2021年5月6日掲載)
この言葉の通り、2018年に入ってふたたび彼の中から湧き出してきた新しい音楽は、現実からフィクションへの逃避をテーマに持つ『Worlds』とも、彼がそれまでにリリースしてきた他のどの作品とも似ていない音楽だった。それは彼が『おおかみこどもの雨と雪』のサウンドトラックの中で一番好きだと話している「めぐり」と同じように、現実の中に、手で触れることのできる日常の中に、美しく親密な何かを見出している音楽だった。
その年の秋、恋人とともに日本に滞在していた彼は高木正勝から自宅に招かれるという幸運に恵まれる。上で引用したFADERのインタビューによれば、ポーター・ロビンソンは高木の著書『こといづ』でもその生活の様子が仔細に綴られている兵庫県の山間にある小さな村を訪れると、自己紹介もそこそこに、彼のサウンドトラックが自分の世界観をどれだけ変えてしまったかということを高木に伝えたという。あの映画ではゆりかごに揺られているような、赤ん坊を抱いた母親が両腕を揺らすときのような音楽を作りたかったのだ、と答えながら、高木はそれをわかりやすく示すように、背後にあったピアノで「めぐり」のメイン・メロディーを弾いてみせる。会話を続けながら、ポーター・ロビンソンは涙を必死に堪えていたという。「高木さんの音楽は、まるで野原で草花の中に横たわっているみたいな感じなんだ」とblock.fmに語っている彼は、『Nurture』のジャケット写真をその通りのものに仕上げ、4曲目の「Wind Tempos」には高木が弾くトイ・ピアノにエフェクトをかけた0.5秒ほどのサンプルをお守りのように忍ばせることになる。
他の曲が次々と出来上がっていく一方、最初のメロディーが降りてきて以来、「Something Comforting」は手つかずのままになっていた。この曲では落ち込んでいた時期に感じていた筆舌に尽くしがたい苦しみを歌いたいと思っていた、と彼はその理由についてAtwood Magazineに話している。しかしその作業があまりにもつらく、スタジオで一人泣き崩れてしまうような状態が続いていたのだという。どうしても歌えないものを歌うにはどうしたらいいのか? そんな自問の末に彼が辿り着いたのは、ある1つの仕掛けだった。
ピッチ操作的なものを自分の声にまとわせて、そこにフェミニンでキュートなキャラクターを与えてみると、それがすごく役に立ったんだ。どんなことでも言えるような気がした。まるで仮面をつけるみたいに、自分が感じている本当のことを言えるようになった。きっとそれが僕にとって恐ろしすぎることだったからだと思う。自分の現実の声で、正直に歌うことが。だからこの音声加工という仮面をつけたことによって、望むままに心を開くことができるようになるための一歩を踏み出せたんだ。
Song Exploderのインタビューから(同上)
もともとマデオンがアルバム『Good Faith』(2019)で声を低く加工して用いていたことに感銘を受けていた彼は、スタジオでさまざまな実験をおこなった結果、逆に声を1オクターブ上げれば音楽的に面白い効果が生まれるだけでなく、それが一見可愛らしい女性の声に聴こえることによって自分を完璧に覆い隠してくれること、その影からありのままの思いを語れることを発見した。まさに「仮面の告白」そのものだが、この手法によって彼は『Worlds』で手にした成功をもう一度求めてしまい(「手に入れるほど欲しくなって」)、そのために努力すればするほど何も作れなくなってしまった自分(「希望を持つほど傷つくなんて」)に対する自責の念(「ああ自分はきっとどこかがおかしいんだ」)や無力感(「誰かかけてくれないか 励ましの一言を」)を、初めてさらけ出すことができるようになったのだ。
しかし彼がやりたいのは仮面をつけて言いたいことを言うことだけではなかった。肝心なのは、その仮面の奥に素顔の自分がいることを最後には勇気を持って明かすことだった。それこそが自分の脆さを本当に受け入れ、つらい体験の中に意味を見出すことに他ならなかった。彼は『Something Comforting』の2度目のサビで自分自身を登場させ、最後のサビではヴォーカルを切り替えるスイッチを何度も繰り返し動かすことで仮面を少しずつ剥がし、女性ヴォーカルの正体が自分であることを種明かしすることにした。
あの最後のセクション––––今こうして話している僕の自然な声と、このレコードで多用している、エフェクトをかけた声が交互に現れるあのセクション––––のために、僕はこの曲(「Something Comforting」)を最初に発表する曲にしたいとずっと思っていた時期があった。僕はあのセクションがいわば説明になっているところ、僕自身であるところが好きなんだ。なぜなら歌っているのが僕であるというのがすごく重要なことだったからだ。
Twitterの動画メッセージから(2020年3月11日投稿)
最終的にアルバムからの1stシングルとして選ぶことになった「Get Your Wish」のための声明に、彼は「生産性や達成によって自分の問題が解決するという期待をもって音楽を作るべきではなく、音楽が僕を感動させるように、自分の正直な表現が人々を感動させるだろうという希望をもって音楽を作るべきなのだということに気がついた」と書いている。成功を追い求め失敗を恐れるあまり、「自分を証明する」という危険な沼にはまってしまった彼を救ったものは実際のところ何だったのだろう。「Sweet Time」や「Blossom」などで歌われている恋人の存在はもちろん大きかったはずだ。しかしこのアルバムが『おおかみこどもの雨と雪』の影響を受けていること、アルバム・タイトルである「Nurture」が「何かが育ちつつあるとき、それをケアし、励まし、サポートすること」(オックスフォード英英辞典)という意味を持つ言葉であること、そして「Mother」という収録曲があることは、それ以上に彼の中で母的なものが果たした役割の大きさを窺わせる。
何かを育てていくことに関して、アーティストと母親にはとてもよく似ているところがある。ほとんど何の能力も持たない赤ん坊に母親(または母的なものを提供するその他の養育者)が絶望せずにいられるのは、赤ん坊がいつかたくさんの能力を身につけていくことを信じて疑わないからだ。そんな母親の前で、子どもは「自分を証明する」必要がない。ゼロから作品を生み出すアーティストは––––そして自分の内に何かを育みたいと願うすべての人は––––それと同じような忍耐と信念を胸に自分自身と向き合う必要がある。「両親の家を出ることを決断したこと、自分は大丈夫だし、物事もうまくいくと気づいたこと、幼少期の思い出を手放すという悲しみを乗り越えて前進したことは、僕のクリエイティヴ面においてとても重要だった」と『Nurture』の制作中に実家を離れたことについてポーター・ロビンソンがビルボード・ジャパンのインタビューで語っていることは、このアルバムの制作過程が彼にとって母的なものを現実の母親から彼自身の内へ移行させる巣立ちの過程でもあったことを示しているように思える。
私が『Nurture』を聴くたびに何か大切なものを思い出すような感覚を持つのは、もともと「自分から決して逃げない勇気」を持っていたポーター・ロビンソンが傷だらけになりながら獲得した、そんな「自分に対する優しさ」のためなのかもしれない。何よりもまず自分が自分を「ケアし、励まし、サポートする」こと。この一度限りの人生を自分らしく歩んでいこうとするとき、それ以上に大切なものが他にあるだろうか。